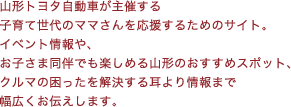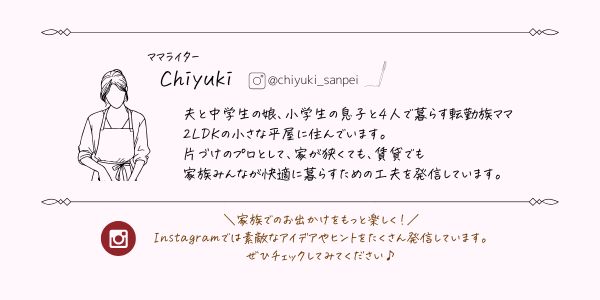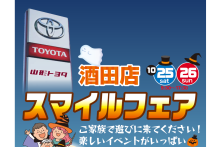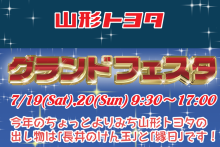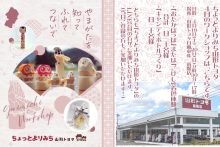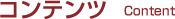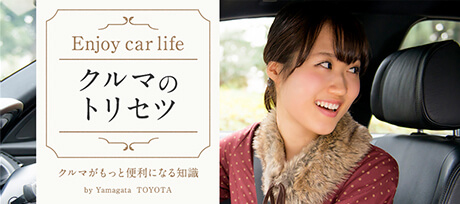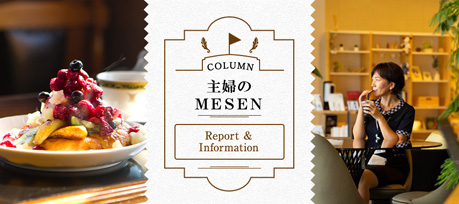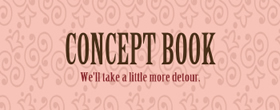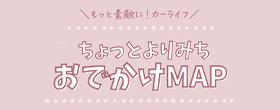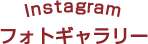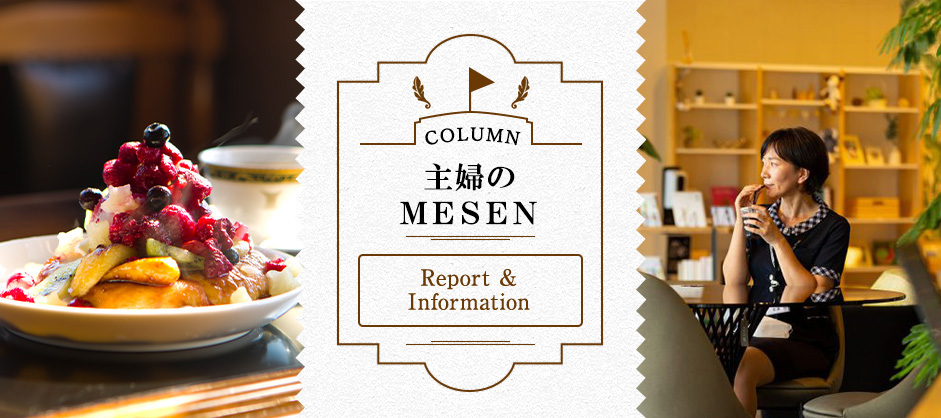
子どもの命を守る第一歩!「防災ポーチ」今すぐ準備しませんか?
いつ起こるかわからない災害。子どもが小学生になると、親と離れて行動する時間が長くなるので、いざというとき一人で対応できるか?心配ですよね。そんなとき、「少しでも子どもたちの助けになれば・・・」という思いから、子どもたちに防災ポーチを持たせるようになりました。今回は、わが家の防災ポーチをご紹介します。

■忘れがちな情報は「防災カード」にまとめて
わが家には中学2年生の娘と小学5年生の息子がいます。2人とも学校や習い事などで親と離れて過ごす時間が増えてきたので、災害時に連絡が取れるのか?きちんと落ち合えるのか?など、考えるとやはり不安があります。そこで、そんな不安を少しでも解消できるよう、まずは「防災カード」を作りました。
カードには、家族写真・名前・住所・家族構成・家族の連絡先・持病・アレルギーなどの情報、それから家族で決めた避難場所や災害用伝言ダイヤルの使い方などを載せています。

もし、家族と離れ離れになってしまっても、家族写真があれば、家族を探してもらうとき、少しはスムーズになるかもしれませんし、状況に応じた避難先が書かれていれば、少しは早く会えるのでは?という思いからです。
また、災害用伝言ダイヤルはなかなか使う機会がなく、存在すら忘れてしまいがちなので、いつでも使えるよう使い方をカードに記載しました。

災害用伝言ダイヤルは、毎月1日・15日、正月・防災週間などに体験することができるので、年に1~2回家族みんなで練習するようにしています。

防災カードは濡れてボロボロになってしまうと困るので、100円ショップで購入できるセルフラミネートシートなどで保護してから、防災ポーチに入れておくと安心ですよ。
■防災ポーチに入れるアイテムは必要最低限で
防災ポーチには、さまざまな場面を想定していろいろなアイテムを入れておきたいところですが、あまり欲張って入れてしまうと、重くて持ち運びが面倒になるので、必要最低限のアイテムに絞り、なるべくコンパクトにまとめてポーチに詰め込んでいます。
ポーチの中身はこんな感じです。

- 防災カード&保険証のコピー
- 絆創膏・コンタクトレンズ・薬など
- マスク
- 携帯用トイレ(習い事用のみ)
- コンパクトレインコート
- アルミブランケット
- 流せるウェットティッシュ
- カイロ(冬のみ)
- 携帯うちわ(夏のみ)
- 圧縮タオル(習い事用のみ)
- 小銭(習い事用のみ)
- 飴・塩分タブレット(習い事用のみ)
ポーチの外側には、ホイッスルとキーホルダーライトも取り付けました。
なるべくコンパクトにまとめるため、ハンカチやティッシュなど、常に持ち歩いているアイテムは省いています。また、小銭や飴は学校に持って行くとトラブルになる可能性があるので、習い事やお出かけの際に持ち歩く防災ポーチにだけ入れました。必要なものはお子さんの年齢やライフスタイルによっても変わってくるので、親子で話し合って中身を決めると良いと思います。
どのアイテムも100円ショップで手軽に購入することができますが、中には使い慣れないアイテムもあるので、一度子どもと一緒に使ってみるのがおすすめです。せっかく持っていても、使い方がわからなければ意味がないので、使い方が難しそうなアイテムは一度試しておくと安心ですね。
■定期的な見直しで防災意識を高めよう
防災ポーチも一度作ったらそれで終わりではありません。季節によって必要なアイテムが変わりますし、アイテムの使い方を忘れてしまうこともあるので、わが家では確認の意味も込めて、9月と3月の年2回は見直しをするようにしています。

親子で防災ポーチの中身を見直す時間は、「災害時にどう行動するか」「どこに避難するか」などを話し合う良いきっかけにもなっています。
できることなら、防災ポーチが活躍するような事態が起きないことが一番ですが、「いざというときに困らないための備え」をしておくことは、子どもの命を守るための第一歩。
小さなポーチに詰め込んだ“備え”が、きっと大きな安心につながるはずですよ。
こちらの内容は
家事のMIKATA「”もしも”に備える 100均で作る防災ポーチ」(動画)でもご覧いただけます。
人気記事をランキング形式でお届け♪